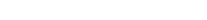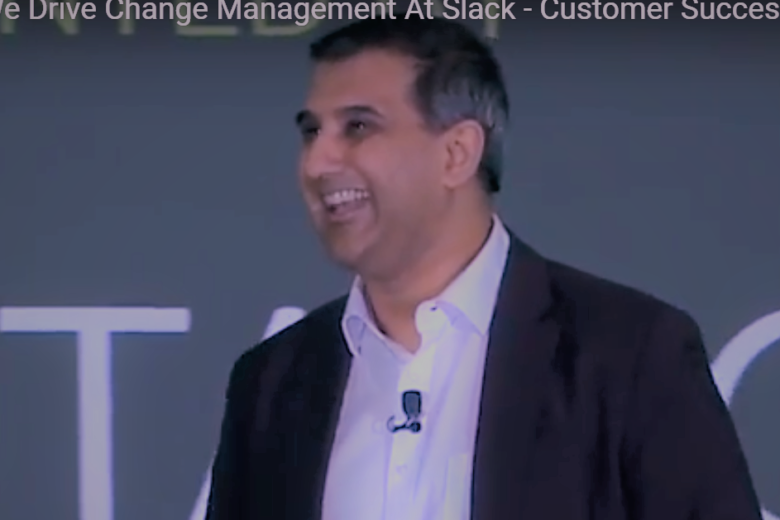
Slack社のカスタマーサクセス責任者 ロブ・ダリウォルさんが、カスタマーの職場で働き方を改革することがいかに難しく、かついかに重要か、そしてSlackはそれをどうやっているかお話しされます。
” Slackは超簡単、働き方を変えるのは超難しい “
「どんなに最高なソリューションでも使われなければ意味がない」はLinkedInペリーさんの言葉ですが、本当にその通りですね!
ソリューションが画期的で超簡単なほど、カスタマーサクセスはテクノロジー問題よりピープル問題、つまりコンサルティング会社が手掛けるようなチェンジマネジメントがメインになるようです。
これ、心当たりのある方、多いのではないでしょうか?
Slack社でのチェンジマネジメントの進め方
こんにちは ロブです。皆さん、私が綺麗な英語を話す英国人だと思ったかもしれませんが、そうならお詫びしますね。おまけに時差ボケでカフェイン飲みすぎたので、もし話しが速すぎたら休憩で私をつかまえてください。ぜひ1対1でお話しましょう!
私はSlack社がカスタマーサクセスを立ち上げた3週間目に入社した米国以外の初メンバーで、同チームの組成に関わる幸運を得ました。具体的にはロンドンオフィス開設を担当しました。最初の数ヵ月は我が家のダイニングルームみたいなオフィスでしたけれど。
Slackについて少しご説明します。Slackは身近な人とのメッセージアプリです。あなたと仲間を繋ぐように設計され、毎日の仕事で使うツールです。私たちの使命は「人々の生活をより働きやすくシンプルで楽しく生産的にする」です。
お陰様で、私たちの使命は皆さんに受け入れられ、昨年末現在の日次アクティブユーザーは400万人になりました。収益源も世界中にどんどん拡大しています。

私たちのプロダクトは、皆さんの毎日の仕事で無くてはならないものです。実際、とても多くの時間を使ってもらっていて、具体的には1日2.3時間以上です。
これ無しでは仕事にならないという存在になること(Stickiness)が凄く重要です。私たちのプロダクトをそういうものにしたいです。
そのための最善の方法は何だと思いますか? それは、プロダクトがカスタマーにとって価値がある、もっとストレートにいうと、事業のボトムライン(利益)に大きく貢献するのを実証することです。
それには、Slackであろうとなかろうと、とにかく何よりも使ってもらわなければなりません。従って、?“アダプション” を成功させることが絶対的に重要です。
皆さんこう思ってませんか? 「ウチのプロダクトは超イケてて、誰もが使いたくなるモンなんだぜ! … で、アダプションの課題って何さ?」と。
アダプションの課題とは、図の2人の男性の課題です。皆さんこの2人、身に覚えあるでしょう?

右の若者を仮にジャスティンと呼びましょう。ジャスティンは開発チームで働く超イケてるエンジニアです。彼はTechCrunchのSlackに関する記事を読んで感動し「これマジヤバイ!! クレカで即買い!!」と言い、300人位のエンジニアが使い始めた頃にはとっくに使いまくっている男です。
そしてジャスティンが働く会社は、「これはかなり良いね。ちゃんと調べてみんなで使ってみよう」と言う会社です。
一方の残念なボブ。ボブは会計部門で働いていて、Slackのことは全く知らず、気にもなりません。彼はメール、シェアポイントなどを使っていて何の問題も感じていません。
これがアダプションの課題の本質です:
ボブはSlackを使うよう指示されました。ジャスティンはSlackを使いたいと熱望しました。
つまり私たちは、ボブが働き方を変え新しいツールに慣れるのを手助けする必要があるのです。
下記は当時ネスレのCIO ジェリー・ダンの言葉ですが、アダプション課題の本質を突いています。
Slack is easy. Change is hard.
“No major software implementation is really about software. It’s about? change management… When you move (systems), you are? changing the way people work… You are challenging principles,? their beliefs and the way they have done things for many years”
Jeri Dunn, VP and CIO of Nestlé? 2002
私たちが新しいソフトウェアやサービスを市場に投入する時、本当の山場は実は技術に関わる所ではありません。私たちが新しいサービスを市場に投入して実現したいのは「人の働き方を変える」ことです。
そして「変化」は本当に難しいことです。私にはチェンジマネジメントのコンサルティングが専門の友人がいますが、彼によると変化を好む唯一の人間は濡れたオシメを変えて欲しい赤ちゃんだけだと。
さて私たちは一体何をしたと思いますか?
私たちはもの凄く多くの時間をかけてこの課題を考えました。働き方を変えるのに手助けが必要な世界中のボブさんたちについて、彼らをどうしたら変えることができるか、徹底的に考えました。
結論は「チェンジ&アダプション手法」です。
私たちが編み出したこの手法を今から説明します。実際にカスタマーへ説明することを想定し、なるべく説明しやすくかつ分かりやすいシンプルな設計にしました。

この手法は、技術と変化に対する “ピープル問題” に焦点を当てます。
大分類として変化のフェーズ別に全体を分け、各フェーズがそれぞれいくつかの目的を果たし、かつSlackへの意識が上がるよう設計しています。なお私が単に「Slack」と言う時はプロダクト名を意味します。
基本的に Slackへの意識を高め、使いたいという欲求を作り、使い方に関する知識を提供し、日常業務での問題解決にその知識が使われるよう設計しています。最も重要なのは「新しい働き方に慣れて使い続けてもらう」点です。
私が Slack 社内外の多くの経験から学んだのは、ある人がプロダクトを継続して使わない、つまり新しい働き方に周囲を巻き込まないなら、プロダクトは決して「無くてはならないもの」になりません。多くの先入観が変化を受け入れる邪魔をしてそれがずっと尾を引くかもしれません。
それぞれを見てみましょう。
1. 人と目的
「人と目的」は変化の必要性を定義することです。事業を推進する上でなぜその変化が必要なのか理解した人は、変化をより受け入れる傾向があります。事業推進の観点から変化が必要な理由は複数あります。
Slackを事業で使う理由を定義する。1人ひとりが働き方を変えるのを手伝うチームを組成する
良い事例を紹介しましょう。Slackをカスタマーの事業で使う理由です。
目標:スラックを活用することで、営業、R&D、プロダクションの部門間コミュニケーションを緊密にし、プロダクトの出荷リードタイムを20%削減する
この事例では、営業、R&D、プロダクションの3部門 が私たちのプロダクト Slack を活用することで、彼らのプロダクト出荷リードタイムを20%削減することが目標です。
そして指標で進捗を測定しす。 Slack を導入し、皆さんに働き方を変えてくださいと伝えたら、 「20%削減の目標に向かって効果はでているか?」を指標を使って測定します。
でもそれは成功方程式のごく一部です。より重要な他の大部分は「人/ピープル」です。
人の働き方を変えるのは中の人にしかできません。社外の人間が強制できるものではありません。
私たちは数多くの企業の働き方を変えるのに成功した経験から確信をもって言えることがあります。それは、カスタマーの会社の変化をリードして事業で成功するのに必要なことを教育するなどの支援はできても、会社で働く1人ひとりが変化を自分事としてとらえ会社全体が変わっていくには社内の人の協力が不可欠だということです。
特に「エグゼクティブ・スポンサー(訳者注:役員クラスの人で変化の活動を陰に陽に後押ししてくれるゴッドファーザーのような人)」と「ミドルマネジャー」の存在が最も重要です。彼らの協力なしでは決して成功しません。
はい、皆さんが今何を思ったか分かりますよ。「そりゃあ、エグゼクティブ・スポンサーがプロダクトの導入を後押ししてくれたら理想だよなあ」でしょ?。
理想ではありません。エグゼクティブ・スポンサーに活動を後押ししてもらうことは絶対マストです。
それも、誰もが目にする形でです。エグゼクティブ・スポンサー自身が実際にそれを毎日使い、凄くいいねと宣伝し、周りに使うよう勧め、事業目標や事業ニーズに照らして使わないことの損失を説明してもらうんです。特に最後の点は、変化が必要な理由を説明するのと同じくらい重要です。
ミドルマネジャーは、部門内や事業レベルで活用事例をつくり広めていく上で絶対に不可欠です。人の働き方を変えるには事例が必須です。ミドルマネジャーは人が働き方を変える際に生じる質問に答え、苦労している人を手助けする役割も担います。
2. 活用事例
「活用事例」という言葉、皆さんよくご存じですよね。今回の例で言えば、Slackをカスタマー1人ひとりに自分事として意識してもらうためのものです。
私たちが学んだ重要なことの1つは、活用事例はそれに適した成熟度(マチュリティレベル)があるということです。成熟度が合っていない活用事例を適用しようとすると、過剰な変化を強要し過ぎてユーザーが拒否反応を起こしかねません。
従って誰もが実行しやすい超簡単な事例をつくることが大切です。たとえば Slackでニュースレターを公開するとか、Slackでエグゼクティブを囲む会をつくるなどです。必要な作業が最小限で、使いやすくて、本当に簡単なものです。
その後に、徐々に毎日の仕事に関連させていきます。最初の簡単な事例で Slackの使い方に慣れてもらい、それを毎日の作業に応用してもらうわけです。
ここの例はプロジェクトマネジメントです。Slack はマーケティングプロジェクトを組成し社内のあらゆるマーケティングツールを統合して1か所に集約します。到達したい最終的な理想形は、Slackをクライアントのコア事業プロセス、たとえばプロダクトの部品の注文をSlackで行うなど、にはめ込むことです。
しかし、そのようなとても複雑で影響も大きいプロセスをいきなり変えようとすると、変化によるマイナス影響が出ることを私たちは学びました。
小さく初めて大きな効果に至る活用事例から着手するべし
3. セットアップ
「セットアップ」も皆さんよくご存じですね。私たちは多くの時間を使ってプロダクトを導入・設定し、またカスタマー1人ひとりが導入・設定するのを手伝います。
我々が働き方改革プロジェクトで必ず実施するのは、ユーザーがSlackのコンプライアンスやサポートに関する問い合わせをしたい時どこへ連絡すればいいのか分かり、実際できているか確認することです。
アダプションに必要な技術面のハードルは取り除くべし。
誰もがSlackを利用でき、必要なサポートも受けられるようにせよ。
詳細説明は割愛しますが、アダプション上の障害を取り除くことをしていきます。
私たちは、 サービス規約に準拠さえしていれば、 ユーザーさんがどんなデバイスで作業していても Slackを利用できるようにしたいと思っています。
そして最も重要なのは、問題が生じた時にどこへ問い合わせればいいか分かっていて、かつきちんとサポートを受けられることです。
私たちの経験では、そこは私たちが確実にフォローしない限りユーザーさんは放置しがちです。
様々な研究やデータが証明していますが、人は働き方を変えようとしている際に問題が生じて問い合わせした時の対応がひどければ、もう二度と働き方を変える気にならない可能性が大きいのです。
4. チェンジ
最後にチェンジ、変化の方法論をご紹介するのは変な気もしますね。でも「変化」は働き方改革の全ステップを支えるものなので「変化」というセクションを敢えて設けました。
Slackを使うことへの意識を高め、使いたいという欲求を刺激し、使うための知識を与えるために様々なことをします
ここで強調したいのは、働き方を変えることへの意識を高め、Slackというプロダクトを使いたいという欲求を刺激し、使うための知識を与えるために様々なことをする、それと同時に新しい働き方を定着・維持させるためにも様々なことをする必要があるという点です。
変化は長続きしなければ意味がありせん。Slackが導入され日々の仕事で使われ始めたら、使えずにオロオロする人はゼロでなければなりません。
(1) コミュニケーション
成功の鍵はコミュニケーションです。Slack導入の前・最中・後を通じてエグゼクティブ・スポンサーは変革をリードして明快なメッセージを発し続け、ミドルマネジャーはSlackを使う必要性・使わないリスクについて明快なメッセージを発し続けることが大切です。特にミドルマネジャー自身が、Slackを使うと仕事上でどんないいことがあるのか、具体例を示し自ら変化をリードすることが大事です。
そういったコミュニケーションは複数のチャネルを活用して展開します。イントラネットや電子メールはもちろん、個別ミーティングやチームミーティングも活用します。
(2) トレーニング
変化の火付け役になる人たちをトレーニングすることは非常に意味があるのでカスタマーサクセスのプロの時間をそこにも多く割きます。
Slackが考えるトレーニングは2つの部分があります。1つはSlackというプロダクトの使い方、つまり用語、特徴、各機能に関する知識を伝えること。
もう1つのより重要な部分は、その知識を実際にプロダクトを毎日使える力へ変換することです。具体的には役員、Slack管理者、一般社員、チャンピオン(訳者注:最も優れた使い手)ごとの活用事例をそれぞれの人が実際にできるようにします。
ここまではプロダクトについての説明でした。次は、その特徴や機能を実際に毎日の仕事でどう使うとどんないいことがあるのか説明します、というわけです。
(3) 継続的な意識付け
最後は継続的な意識づけ、要は、働き方改革を継続・維持することです。Slackの導入が終わった、アダプションが終わった、とたんに変化が止まっては意味がありません。
我々は全員が変化し続けられるよう、新しい働き方を継続する秘訣や成功事例を共有したり、変化の勢いを止めないための努力をします。そうしなければ、せっかく生れた変化の動きが座礁に乗ったり、脱落者が生まれたり、結局昔の働き方に逆戻りするリスクが非常に大きいからです。
以上が「チェンジ&アダプション手法」の説明でした。どういう話でしたっけ?ご安心ください、皆さんにテストするつもりはありませんよ。
私たちSlackでは、この4つ、即ち「人と目的」、「活用事例」、「セットアップ」、「チェンジ」を同時並行で進めます。

最初の「準備」には 数週間かけ、カスタマーと共に計画を念入りに磨きます。
その後、初期導入グループへ試し展開します。そこでフィードバックを得るため一旦立ち止まります。コミュニケーションが上手く展開できてるか、適切な人を巻き込めてるか、プロダクトの活用を妨げている技術的な障壁は何か、などを確認します。そうやって必要な調整を加え次のグループへ導入していきます。
この段階で私たちは初期導入グループでの経験から皆さんの変化への受容度を理解していますし、更に学び続けているので、次のグループへ展開するにつれ変化の動きは加速的にどんどん大きくなります。
上手くいくとこんな感じです。

この前半の長く平坦な時期に、Slackを使った新しい働き方を試行錯誤するユーザーがいます。私たちは彼らと一緒に変革プログラムをつくります。そこに集中して時間を使います。
するとやがて直ぐに Slackの活用度が大きく跳ね上がります。理想的にはその後に大きな変革の波が生まれるので、私たちはその跳ね上がりがいつか、いつかと楽しみにしています。
そしてアダプションの成功が早ければ早いほど、収益は加速的に増え契約もどんどん更新されます。
まとめ
私が話したポイントは3つです。
1つ目は、アダプションは新しい技術を導入するということ以上の意味があります。それは人びとの働き方を変えるということです。1人ひとりの働き方を変えるのを手助けするということです。
2つ目は、人が長年なれた働き方を「変える」のは本当に本当に難しいということです。
3つ目、もし今日のポイントを1つに絞るならこの3つ目ですが、1日も早く変革に着手すべし!です。
調査によれば、Slackのようなソフトウェアを利用することで包括的な働き方変革プログラムを推進したカスタマーは、そうでない企業に比べ、事業目標を達成する確率が6倍高いです。
一方残念なことに、そんなことはないだろうと考えるカスタマーも多いです。
カスタマーサクセスのプロである私たちの仕事は、そういうカスタマーこそ契約前のセールス段階から早々に教育を施すことです。そうすることが長期的な視点でカスタマーの成功に繋がり、結果より多くの契約更新に繋がるからです。