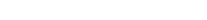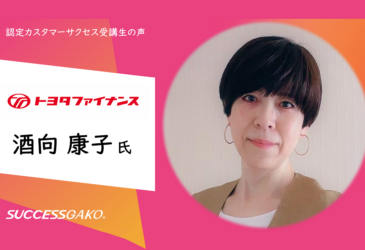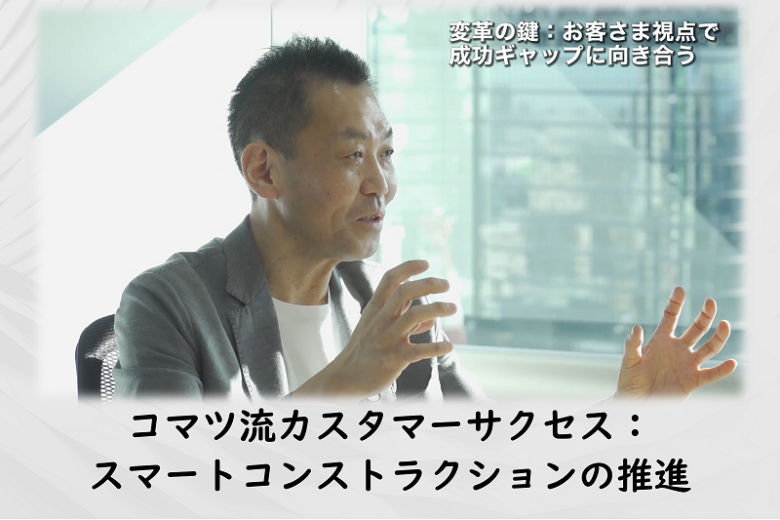
![]() by 稲田 和絵
by 稲田 和絵
2015年の誕生以来、進化を続けるコマツの『スマートコンストラクション』。
成功の裏には、「お客さま視点に立って考える」企業文化をはぐくんできたブランドマネジメント活動、そして社長の強いリーダーシップがありました。進化を前線でリードされてきたスマートコンストラクション推進本部長の四家千佳史さんに、誕生秘話から取組み中の挑戦までお話を伺いました。
なお、スマートコンストラクションについて弘子ラザヴィの解説も加えたインタビュー動画「コマツ流カスタマーサクセス:スマートコンストラクションの推進」も、ぜひ併せてご参照ください
<ゲストスピーカー>
四家 千佳史 氏
コマツ 執行役員 スマートコンストラクション推進本部 本部長 兼 EARTHBRAIN 代表取締役会長
<ナビゲーター>
弘子 ラザヴィ、サクセスラボ 代表
<目次>
四家様のご経歴
弘子ラザヴィ(以下、弘子):
最初に、四家さんの簡単なご経歴と現在の役割について教えてください。

四家 千佳史 氏(以下、四家):
私は今、コマツという建設機械メーカーにおります。
29歳の時に、ITを使い倒すビジネスをしたくて、建設機械のレンタル会社を設立しました。10年ほどで、700人規模に急成長しました。その会社と当時コマツの子会社だったレンタル会社とで経営統合することとなり、コマツグループに入りました。
コマツ子会社のレンタル会社で、私は社長を8年ほど務めました。
そして2015年、スマートコンストラクションをスタートする際、コマツの執行役員として、スマートコンストラクション推進本部長に就任しました。
2021年9月には、コマツのスマートコンストラクション企画開発部門の一部をカーブアウトし、株式会社EARTHBRAINという会社を設立しました。現在は、コマツのスマートコンストラクション推進本部長と、EARTHBRAINの会長を兼務しています。
スマートコンストラクションの誕生とその後の進化
弘子:
スマートコンストラクションは、誕生してからこれまでどのような変遷を辿り、そして現状はどのようになっていますか?
四家:
私どもコマツは建設機械メーカーですから、自分たちの製品、ハードウェアで良いものを提供できればお客さまの課題を解決できるだろうと、当初は思っていました。そこで、当時最新のICT化された建設機械、つまり、自動制御、半自動制御できる機械を世に出したわけです。
しかし、機械の性能が良いだけではお客さまの課題が解決できないということを、コマツはその時に理解しました。
今までの、自社の製品ありきでお客さまの課題を考えるというやり方ではなく、お客さまの現場、お客さまのオペレーション上に立ち、お客さまと一緒に課題を見つけて、それを解決する取り組みをしていく。そう意思決定したのは、2015年1月のことです。
完全にゼロからスタートしました。お客さまの課題を見つけては、解決できることを1個1個、なるべく早くリリースし、ありたい姿に一歩ずつ近づける。この繰り返しをひたすら続けました。
最新の転換点(2019年):ドイツの現場で考えた目指すべき真の「現場のDX」
四家:
2015年から、がむしゃらにお客さまの課題を理解して解決しようと突き進んできました。しかし、ある時ふと振り返って、気づいたのです。「私たちがしていることは、お客さまの仕事を単にデジタル化しているだけなのではないか?」と。
確かに、例えば今まで2人1組で測量していたことを、ドローンを10分間ほど飛ばすだけで高精度な3次元の測量データが得られるようになったのは、大きな変革です。しかし、お客さまの施工プロセス全体から考えると、既存のプロセスがなくなったり、新しいプロセスができたりしているわけではなく、今までのプロセスが単にデジタル化しているに過ぎません。
我々のありたい姿、お客さまのありたい姿を目指すには、各プロセスをただデジタル化していくだけではおそらく行き着かない。そう考え、我々は一度立ち止まりました。
「我々が目指すべきところは一体どのようなものなのか。それを見つけるために、もう一度現場に行ってみよう」と。
日本の現場ではなく、建設工事のデジタル化が進んでいるといわれるドイツの現場に向かいました。

ドイツでは、たしかに施工前の計画を作る工程などにおいては、多くのデジタルソリューションが使われていました。しかし、驚いたことに、施工中は何もデジタル化されていなかったのです。現場監督が目で見て、頭で考えて、口で指示を出している。
そこで、我々は考えました。「建設現場全体の動きがリアルタイムに可視化されたら、どうなるだろうか?」と。それを前提にプロセスを描いてみると、既存プロセスと全く違うものが生まれてきました。
我々が過去に取り組んできた各プロセスのデジタル化は、決して無駄なことではなく、それらが全て繋がり、現場全体がデジタル化され、高精度に、リアルタイムに把握できるようになるのだと気づいたのです。それまで、現場監督が「報告しろ」と言っていたことが、報告を待たずに一目で分かる。結果、今のプロセスがものすごく短くなる。関与する人も、現場内外問わずとてもコンパクトにまとまる。
「これこそがトランスフォーメーションなのだ」、「私たちの目指す世界はこれだ!」と確信しました。
2019年からは、今までのスマートコンストラクションから、DXスマートコンストラクションへの進化を目指して、再スタートしました。
それ以降、開発する手法やスピード感がガラッと変わりました。これはスマートコンストラクションの大きな転換点だと思います。
変革の鍵:お客さま視点で成功ギャップに向き合う
弘子:
視点を変えたり、変革を達成したりするのに必要な要素は何でしょうか?
四家:
よく皆さんから、「どうしてスマートコンストラクションはうまくいったの?」と聞かれます。特に製造業の方からよく聞かれます。
私の考えとしては、軸をブレさせないことです。
お客さまのオペレーション上に立ち、お客さまの課題を見つけ、我々のいま持つ技術であるかどうかにこだわらず、課題を解決するために最善の手段を世界中から見つけてくること。この軸を絶対にブレさせてはいけません。

弘子:
その軸は、最初からあったのでしょうか?
四家:
コマツでは、15~16年前から「ブランドマネジメント」という活動をしています。これは、我々の目標からお客さまの課題を見つけるのではなく、お客さまの目標とお客さまの現在、このギャップを我々が解決していこうという活動です。
これまでは、たとえば「非常に燃費のよい商品ができました。お客さまは、原油高で燃料代に困っているから、その問題をこの商品で解決できます。」という視点でした。
ソリューションと言いつつも、結局はプロダクトアウト。自分たちの商品の機能で何を解決しようか…と考えていたのです。この考え方では、いつまでたっても機能から離れられません。
私たちは、「自社の建機の機能で物事を見るのではなく、お客さまの現場の一部だけを見るのでもなく、お客さま側のオペレーションに立って全体を見ることが大切なのだ」と、考え方を切り替えました。
コマツはブランドマネジメント活動をずっと行ってきたので、この発想の切り替えに対しても比較的すんなりと社内で受け入れられたように思います。
社長のリーダーシップ:理想像を宣言し退路を断つ
弘子:
変革が成功する裏には、必ず経営層の強いリーダーシップが存在していると思います。コマツの場合、どのような経営者のリーダーシップが、どのような局面で発揮されたのでしょうか?
四家:
スマートコンストラクションの企画を考えたのは、2014年12月頃でした。当時の大橋社長に、スマートコンストラクションのコンセプトとともに、「お客さまのオペレーション全体の最適化をしたい」と伝えた時、その場で「明日発表しろ」と言われたのです。
「明日発表もなにも、コンセプトを描いたこの紙1枚しかありません」と返答しても、頑として聞いてもらえない。12月だったので、さすがに年明けにしてもらいましたが、その間に大急ぎでイメージビデオだけ作り、大々的な発表会を開催しました。社内の関係者も含め、報道陣とアナリストなど300人ほど集めて、まずはコンセプトを発表したのです。
後に大橋は、「あのとき、社長である自分が外に向かって発表することが大事だった。社長が発表したら、誰ももう後に引けないだろう。四家がスマートコンストラクションでこんなことをやりたいと言ったとき、他の役員も協力してくれる。社長自ら発表したのだから」と言いました。
たしかに、「なんであんなものを発表したのだ?」という声があがっても、「でも発表しちゃったからには、やるしかないよな、このスピード感で」とみんな動いてくれました。
まず発表し、後に引けなくしてしまう。外せない梯子にしてしまう。それが、スタート時点で非常に大きかったと思います。
100歳のモノづくり会社、コマツの新たな挑戦
弘子:
「数年後こうしていきたい」という将来の展望をお聞かせください。
四家:
コマツは2021年に100周年を迎えました。我々はモノづくりの会社です。100年間、品質と信頼性を重視して製品を作ってきました。
一方、我々は「コト」と呼んでいますが、お客さまのオペレーションを最適化するためのソリューションも最近は提供しています。
よりスピードを上げて、よりスマートコンストラクションを進化させていくには、今までのコマツのモノづくり文化を変えるのではなく、新しい舞台が必要だと判断しました。そこで、出島として、今回、EARTHBRAINを作ったのです。
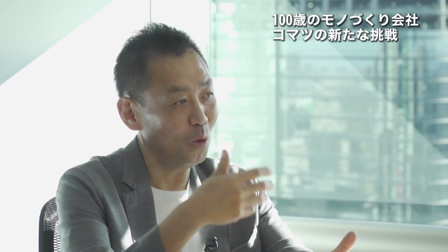
「モノ」と「コト」はあらゆる点で異なります。例えるならば、「モノ」はダンボール箱に入れて工場から出荷する時点で、既に価値がそこに内包されています。うちの機械はダンボール箱には入りませんけれど。
一方、スマートコンストラクションのような「コト」ビジネスは、箱から出して、それをお客さまが使うことでお客さまが儲かって、安全性も高まって… となることで価値を認めていただけます。つまり、使ってからが価値の始まりです。
また、「モノ」は基本的に価値が経年で劣化していきます。しかし、我々の取り組んでいる「コト」は、経過が蓄積されることによって、さまざまなアルゴリズムを生み、価値が増えていきます。
このように、「モノ」と「コト」を比べると、もう全くの別物なのです。
コロナ禍になり、スマートコンストラクションの環境にとっては追い風が吹きました。現場に行かなくても、事務所からデジタルですべて見えるのです。これを進化させるには、どのような成功要件が必要なのか? と現在の小川社長から言われ、いろいろ洗い出しました。
「ジョブ型」「通常の目標管理をやめて、ありたい姿についての高い目標を設定させ、やる気を促進する」「開発手法はアジャイル」など、思う限り書きだしました。それを見て社長が言ったのは、「これ、コマツと全く逆だよね」。
でも、これを実行しなければ、進化は見込めないことを伝えたところ、「そうか。コマツのモノづくりのやり方を変えるわけにはいかないから、スマートコンストラクションを外に出して、出島にしよう」となりました。
現場は屋外にあります。そこでは移動体通信が必要なので、その技術をもった株式会社NTTドコモに入っていただきました。
また、土や石などにセンサーは付けられません。そこで、センサー技術で世界トップシェアを誇るソニーセミコンダクタソリューションズ株式会社にも参画いただきました。
そうしてカーブアウトした会社をJV化し、EARTHBRAINという会社を作りました。現在、どちらかというと私の軸足はEARTHBRAINに置かれています。
今までは5年先ぐらいだと思っていた「ありたい姿」のゴールを、3年、2年、1年と、どんどん近くに寄せていくことに注力していきたいです。
日本のビジネスリーダーへのアドバイスとエール
弘子:
ありがとうございます。聞いていて、本当にワクワクします。
最後に、「全く違うものを始めたい」、「そちらに軸足を移したい」と思っている会社に向けて、何かアドバイスやエールを送っていただけますか?
四家:
何度か申しましたが、トランスフォーメーションする際に、自分たちの製品視点で考えるのではなく、それを使っているお客さま側に完全になりきることです。
例えばBtoCの商品であれば、お客さまが朝起きて、夜寝るまでの間で、何か新しい価値を創造することを考える。
そのとき大事なのは、決して自分たちの製品にこだわらないこと。もちろん、自社のサービスや製品がそこに加わることができれば、それは嬉しい話だけれど、それを前提にしてしまうと、新しい価値は創造できないと思うので。
お客さま側に移り、そこからの視点で考えていくことが非常に大切です。
弘子:
ありがとうございます。
(了)
▼スマートコンストラクションの解説入りインタビュー動画
▼カスタマーサクセスに挑戦する人が、知恵と勇気と仲間を手にする実践者コミュニティ「SuccessGAKO」
SuccessGAKO(サクセスガッコウ)は、日本のカスタマーサクセスの未来を作る変革リーダーを輩出するための学び場です。カスタマーサクセスを追求するビジネスパーソンが、知識や知恵を学び、考え、実行することで、自社、顧客そして自身も成功することを目指します。経験豊富な講師陣による集中講座と、メンバー限定コミュニティにより、一方的に知識を伝授するのではなく、仲間と切磋琢磨しながら「実践」することに価値をおいたプログラムを提供します。
『実践カスタマーサクセス』第3期生募集中
実践カスタマーサクセス第3期を2022年4月に開校します!
詳細はこちら:
(以上)