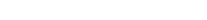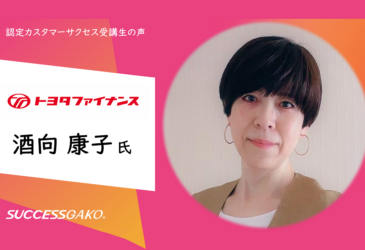サブスクリプションなどに代表されるリテンションモデルやSaaSビジネスが急速に発展している今。企業の顧客志向への転換とともに聞かれるようになった、チーフカスタマーオフィサー(CCO)という名称。これは、1999年に世界で初めて新設された、新しい最上級役職の一つです。
本記事では、CCOの定義や、創成期から現在までの役割の変遷、CCOに共通する3つの目標、そしてアメリカのウォルマート社で活躍するCCOの先進事例などを幅広くご紹介します。
Index
1)CCOとは
・CCOの定義
CCOとは、チーフカスタマーオフィサー(Chief Customer Officer)の略語で、まだ世の中に登場してからとても日の浅い、最上級役員職の一つです。
1999年、アメリカのTexas Power and Light社で、初めてCCO職は新設されました。最初に任命されたのは、Texas New Mexico Power社(TNMP)のCCOであるJack Chambers氏です。
当時それはまったく新しい職種で、“CCOのあり方”についてのMBAプログラムはもちろん、ハーバードビジネスレビューの論文や実態調査など何も裏付けはありませんでした。経営層の中でも、顧客の中でも、その定義は不明確で、役割も十分には理解されていませんでした。
そしていまだに、名刺を顧客に渡すとき、まずは自らの役割が何かを説明しなければならないCCOは多いはずです。
現在、CCOは一つの肩書きとして知られています。
が、その役割を正確に定義するなら、「ある企業において、自社のカスタマーに関する包括的、かつ絶対的な見解を提供して、カスタマーの獲得や維持、そして顧客基盤からの収益最大化に向けた戦略の策定に責任をもつ、最高位の経営幹部」です。
よって、CCOは必ずしも役員職である必要はありません。しかし、彼らの仕事がきちんと効果を発揮するためには、企業内の最上級役員職の一人であることは必須なのです。例外はあるものの、通常、CCOはCEO直下に置かれます。
CCOは、究極的には“カスタマーの権化”。会社内で誰よりもカスタマーのことを深く理解していて、おそらくカスタマー自身よりも彼らのことを熟知する存在です。
なお、CCOとサービス部門副社長(VP)は、定義上、明らかに異なります。
CCOの特徴は、従来の組織上のサイロやビジネスユニットの境界にとらわれることなく、会社全体を見渡したカスタマー戦略を策定して推進していくことにあります。この能力がなければ、個人の権限は限られてしまい、CCOの肩書きも保証されません。
そして何より、CCOはカスタマーに関する包括的なインサイトの洞察と、戦略策定の視野とをすべて動員して、収益性が最も高いカスタマーを獲得し、そして維持していく必要があります。
「チーフカスタマーオフィサー」、「チーフクライアントオフィサー」、「カスタマーエクスペリエンス部門副社長(VP)」など具体的な名称の差異は、重要ではありません。
大切なのは、カスタマーがその肩書きの意図を理解し、カスタマー自身の利益最大化に繋がる行動をその人が提供する力があると認識できることです。
・CCO創成期
2003年にチーフカスタマーオフィサー(CCO)という肩書きを持つ人は、世界でたった20人にも達していませんでした(この中には、Sun Microsystems社のMarissa Peterson氏、Cisco社のDoug Allred氏、Monster社のJeff Lewis氏など、少数の先駆者が含まれています)。
当時は、CCOという職位は知られておらず、そういった名称の最上級役員職が必要なことを理解できていない企業が多かったからです。
初期のCCOは、どちらかというとカスタマーサービスとカスタマーリテンションを主眼にした、「チーフカスタマーサービスオフィサー」と呼べるものでした。
言うなれば、彼らの役割は「お客さまとより良く遊ぶこと」。カスタマーが会社を訴えない方法を探すことに注力する人もいました(残念ながら、現在にもそういう人は少なからず存在しますが)。
CCO職で成功を収めた人は数多いですが、登場初期には困難に直面して早々に退場や引退を余儀なくされる人や、会社の収益が急増した瞬間に追い出された人もいました。心臓発作を起こして引退し、完全に現場を離れてしまった人もいます。
もちろん、すべての人がそのような劇的な運命を辿ったわけではありません。多くの成功者たちが、後続への道を切り拓いたのです。
・CCOの現在
今、世界で500人以上のCCOが活躍しています。さらに、その肩書きは持っていなくても、おそらく同じ役割を果たしている人はさらに何百人もいます。彼らの役割は急速に進化していて、実際、毎月多くのCCOが任命されています。
そしてCCOの役割は、「最高カスタマー戦略責任者」へと進化してきています。
企業内でより収益性の高いカスタマー戦略を構築して、適切にカスタマーを獲得、維持しながらサービスを提供することでより利益を拡大するという目標に、より焦点が明確に絞られてきています。
多くの企業にとってCCOは、「あればよい」ものではなく、ビジネス推進上、そして競争優位性を維持するのに欠かせない源泉となっているのです。
余談ですが、「チーフマーケティングオフィサー(CMO)がいるから、CCOは不要」と言う人は昨今、急減しました。代わりに、「CMOはCCOに置き換えるべき」という極端な意見さえ見られます。
・CCOに共通する3つの目標と課題
CCOの存在意義は、カスタマーに関わる企業戦略を全社のあらゆるレベルに浸透させることです。カスタマーに関する権威ある見解を示せるため、企業戦略の策定、そして将来の戦略推進をリードする立場にあります。
また、CCOは顧客ポートフォリオを定義して、顧客の獲得や維持への努力に優先順位をつけます。そして、より大きな顧客価値を創造し、ロイヤルティを高める顧客戦略の立案者である必要があるのです。
CCOは、業界や在職年数に関係なく、以下の3つの共通の目標を持っています。
1)収益性の高いカスタマーの行動を後押しすること
企業として大切なカスタマーにより多くの時間を費やすには、CCOが収益性に基づくセグメンテーションを行い、カスタマーリテンション、カスタマーロイヤルティ、カスタマー満足度、カスタマーの体験価値などのあらゆるカスタマースコアを向上させる取り組みに力を入れなければなりません。
さらに、適切な利益をもたらすカスタマーを獲得するために、カスタマーへの深い洞察力を営業やマーケティング活動に活かそうとするCCOも今後さらに増えることでしょう。
2)カスタマーセントリック(顧客中心)の企業文化を醸成すること
CCOの最重要な役割の1つは、会社内のすべてのレベルに対して説明責任とオーナーシップを発揮し、カスタマーセントリックの企業文化を力強く醸成することです。
この点に失敗したCCOは、誰も責任を持たないために絶え間なく燃え上がる火消しに終始して、自身も燃え尽きます。ゆえに、CCOはカスタマーへの影響力が最も大きく、最も収益性の高い活動をリードするよう取り組みに優先順位をつけなければなりません。
彼らは顧客にしっかりと顔を向けて、従業員(特に顧客に面していない従業員)が、カスタマー提供価値の向上に集中できるよう支援しなくてはならないのです。
3)CEO、取締役会、同僚、従業員に価値を提供し、その価値を示すこと
CCOという役割は新しく、その価値をまだ十分に理解していない人もいるため、CCOはあらゆるステークホルダー(CEO、取締役会、同僚など)に対して、提供した価値を実証する努力が必要です。
ただ価値の測定は、そもそも難しかったり、時間を要したりもします。そのためCCOは、業績に関する懸念を払拭するために業績評価基準を予め明確にしておくべきです。
また、従来の細分化された組織サイロをまたがるカスタマーの問題に対峙するCCOの広い視野に、少なからず脅威を感じる経営陣もいます。
※出典元:CCOカウンシル「Defining the CCO」の原文を和訳して引用したものです
2)ウォルマート社CCOジェニー・ホワイトサイド氏の事例
・チーフカスタマーオフィサー(CCO)の新設
2018年夏、ウォルマートがチーフカスタマーオフィサー(CCO)職を新設し、アメリカン・エキスプレスの上級役員だった ジェニー・ホワイトサイド氏を招へいすると発表しました。このニュースを聞いた時、筆者は興奮と同時に疑問も覚えました。ウォルマートは米経済誌フォーチュンの世界500社番付でここ数年1位を維持する世界トップ企業。そのウォルマートにCCOがいなかったのか?と。
CCOカウンシルの独自調査「CCO Study 2014」によれば、フォーチュン500にランクされる企業のCCO設置率は10%、フォーチュン100だと22%。つまり世界的優良企業の5社に1社では数年前からCCOが活躍しています。にもかかわらず、世界トップ企業にはCCOがいなかったのです。
CCOといえば俗に「Cスウィート」や「Cレベル」と呼ばれる最上級役員職の1つですが、その要職にウォルマートは外から人を招へいしました。ジェニーさんは就任に際してコメントを発表しています。
「この度私はウォルマートへ参画することにしました。今、とてもワクワクしています。(略)アメリカン・エキスプレスでの20年超におよぶ経験から私が学んだのは、エンド2エンドで素晴らしいカスタマー体験を提供することが何よりも最優先で重要だということです。CCOという新しいポジションはウォルマートにとって大きな第一歩です。カスタマーを常に中心に据えて考え行動することに対する、企業の並々ならぬ情熱を反映しています(略)」
ニュース発表によれば、ジェニーさんはCCOとしてオフライン店舗とオンライン店舗(EC)とをリンクさせることでカスタマージャーニー全体を最適化し、シームレスなカスタマー体験を提供すること、それによる新規顧客の獲得とECの売上拡大に責任をもつということでした。明らかにアマゾンへの対抗策です。売上約56兆円(2018)を誇る業界の雄が、売上約25兆円(2018)の業界破壊者に怯えているのです。
「シームレスなカスタマー体験を提供する」というお題目は、オムニチャネルというバズワードと共に日本でも数年前から度々耳にしていて、そこに新しさはありません。新しさは何といっても、世界のトップ企業がこのお題目を真の意味で実行できていないと認めたことです。同ニュースを伝える各社の論調が「ウォルマートにとって大きな第一歩だ」と概ね好意的だったことから、ウォルマートの改善余地は周知の事実だったことが覗えます。
その後、ウォルマートの業績は好調です。2019年1月期の売上高は5,144億ドル(約56兆円)。後半にかけて業績は大幅に上向き、特に第4四半期(2018年11月~2019年1月)は米既存店の売上高が前年同期比4.2%増、そしてeコマース(EC)の売上高はなんと同43%増を達成しました。
ウォルマートの社長兼CEO ダグ・マクミロン氏は2019年1月期の決算発表で言いました。
「リアル店舗とネット店舗が一体化しシームレスにつながることで買い物がより便利・簡単になることをカスタマーの皆さんは熱望しています。私たちは今それを十二分に理解しています」
これこそ、ウォルマートが新設したCCO職のミッションそのものです。
2018年夏、ウォルマートはCCO職を新設してジェニー・ホワイトサイド氏を招へい。彼女の責任は「リアル店舗とネット店舗(EC)とをつなげてカスタマージャーニー全体を最適化しシームレスな顧客体験を提供すること、それによる新規顧客の獲得とECの売上拡大」でした。着任直後の業績はもちろん彼女1人の成果ではありませんが、ECの売上高が前年同期比43%増という絶好調な業績は、新しい取り組みを始める時のよい追い風になるでしょう。今後の展開がとても楽しみです。
最後に、ウォルマートのCCO職新設が秘める重要な意味を3つ紹介します。
1)ノン-テック業界の歴史ある大企業にもカスタマーサクセスが浸透した
ウォルマートがいよいよ動きました。GoogleでもFacebookでもない、ましてテクノロジー会社でもない。従来のモノ売り切りモデルの代表格ともいえる小売り店舗業界で長年世界一に君臨してきた歴史ある大企業です。
デジタル時代を生き抜くあらゆる企業にとってリテンションモデルへのシフトは不可避ですが、ウォルマートも例外ではありません。リテンションモデルではカスタマーとの関係性が根本的に変わります。ウォルマートも、「モノを届ける」から「成功を届ける」企業へシフトしなければならないのです。それには、約70万人の社員1人ひとりがカスタマーの成功について常に考え行動することが必須。そしてそれこそがカスタマーサクセスの本質なのです。
ウォルマートはそれに気づいてCCO職を新設しました。CCO(チーフカスタマーオフィサー)は俗に「C-スイート」ないし「C-レベル」と呼ばれる、各社に1人のみの最高責任職(CEO、COO、CMOなど)の1つ。CCOならば顧客起点の大胆な戦略を実行に移せる、と判断したのでしょう。逆に、CCOでも大企業の組織の壁を打破して染みついたマインドセットを払拭できないならば、ウォルマートですら死を免れないという覚悟の表れです。
2)「上級経営職は内部昇格」が不文律の大企業がCCOを外部から採用した
ウォルマートはCCO職に外部から人材を採用しました。これが何を意味するかピンとくるでしょうか。
ウォルマートの上級経営職に就くには内部昇格が基本です。すなわち、歴史あるウォルマートの企業文化や、社内のさまざまなお作法や、現場や働く人たちのことを熟知し、同社で実績を上げてそれを周囲に認められてから上級経営職に昇格せよ、が不文律なのです。少なくとも現在の上級経営職の方々は、買収された会社の元CEOを除き、最高でも上級副社長として採用されてから内部昇格で現職に就いています。
そんな不文律を破り、外からCCOとして舞い降りるジェニーさん。彼女の採用を決めたウォルマート経営陣の苦渋の想いや、迎える人たちの「ジェニーって誰?」という好奇心、そして警戒心を抱く人も存在するだろうことは容易に想像がつきます。そうまでしてこの人事を決めた理由は明解です。ウォルマートでCCOを務められる人材が社員約70万人の中に1人もいなかった、ということです。同時に、不文律を超えてでも最高の人材を迎え入れなければならない、という危機感の表れでもあります。
3) CCOは変革(チェンジマネジメント)のリーダー役を期待される
CCOジェニーさんの着任先は、実はウォルマートの本社があるアラスカ州ベントンビルではありません。同社が2年前に買収したJet.com社の本社があるニュージャージー州ホーボケンです。アメリカン・エキスプレスでのキャリアの大半(2002~2018年)をニューヨークで過ごし、ウォルマート移籍時もニューヨーク居住だったジェニーさんにとって、その点は英断の助けになったでしょう。
新任の最高経営幹部の着任先が本社から物理的に離れている場合、一般的にはいろいろな理由がありますが、ジェニーさんの場合はチェンジマネジメントが目的と思われます。歴史ある大企業が、長年培った文化と大きく異なる「変化(チェンジ)」を全社へ取り入れる時、本社や既存事業を担う多数派から物理的に切り離すことで変化が芽の段階で摘まれるのを回避するのは、チェンジマネジメントの常套手段です。たとえば、ERP (統合基幹業務システム)が収益の大半だった事業を「カスタマーへ成功を売る」事業が過半を占めるまでに事業構造を大きく変革するのに成功したSAPが、本社のあるドイツから海を隔てた米国シリコンバレーにイノベーションセンターを開設して変革の拠点にしたのは有名な話です。
モノ売り切りモデルで勝ち続けてきた大企業にとってのカスタマーサクセスは、カスタマーセントリックな企業文化を根付かせるチェンジマネジメントから始まります。ウォルマートはCCOをチェンジマネジメントのリーダーに据えてカスタマーサクセスに取り組み始めたのです。CCOの拠点を敢えて本社に置かないという意思決定からはその本気度が伝わってきます。
以上3点がウォルマートのCCO新設に秘められた重要な意味です。米国企業の事例ですが、リテンションモデルにもカスタマーサクセスにも国境はありません。日本企業にとって参考になる点がきっとあるはずです。
最後に少しだけ話をジェニーさんに戻したいと思います。
LinkedInの情報によると、彼女は1993年に大学を卒業し、新卒で入った会社を経て、1997年にアメリカン・エキスプレスへ入社。以降、ウォルマートに抜擢される直前までの20年超、さまざまな経験を重ねています。おそらく40代後半。経験と体力が丁度バランスし、ビジネスパーソンとして脂ののった女性と思われます。ぜひウォルマートで功績をあげ、その次のキャリアを華々しく重ねてほしいと、同じ女性の1人として願うばかりです。
※出典元:弘子ラザヴィ著『カスタマーサクセスとは何かー日本企業にこそ必要な「これからの顧客との付き合い方」』(英治出版・2019年)より、一部加筆修正をして抜粋しています
監修
弘子ラザヴィ Hiroko Razavi

経営コンサルタント。サクセスラボ株式会社代表取締役。一橋大学経営大学院修士課程修了。大学3年次に日本公認会計士二次試験合格。公認会計士として数多くの企業実務に触れたのち、経営コンサルタントに転じる。ボストンコンサルティンググループでは全社変革・企業再生プロジェクトを、シグマクシスではデジタル戦略プロジェクトを多数リード。2017年、スタンフォード経営大学院の起業家養成プログラムIgniteに参加するためシリコンバレーに在住した時にカスタマーサクセスに出会う。帰国後、サクセスラボ株式会社を設立。シリコンバレーで築いたネットワークを活かし、カスタマーサクセスに本気で取り組む日本のビジネスパーソンを支援している。また、カスタマーサクセスに関する情報を日本語で紹介するサイト「Success Japan(https://success-lab.jp/successjp/)」の運営などを通じ、カスタマーサクセス市場の成長・活性に努めている。
▼カスタマーサクセスに挑戦する人が、知恵と勇気と仲間を手にする実践者コミュニティ「SuccessGAKO」
SuccessGAKO(サクセスガッコウ)は、日本のカスタマーサクセスの未来を作る変革リーダーを輩出するための学び場です。カスタマーサクセスを追求するビジネスパーソンが、知識や知恵を学び、考え、実行することで、自社、顧客そして自身も成功することを目指します。経験豊富な講師陣による集中講座と、メンバー限定コミュニティにより、一方的に知識を伝授するのではなく、仲間と切磋琢磨しながら「実践」することに価値をおいたプログラムを提供します。
『実践カスタマーサクセス』第3期生募集中
実践カスタマーサクセス第3期を2022年4月に開校します!
詳細はこちら: