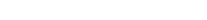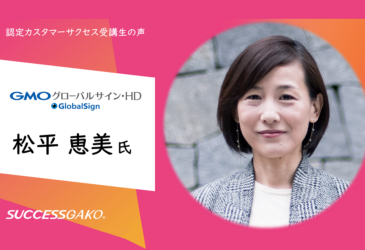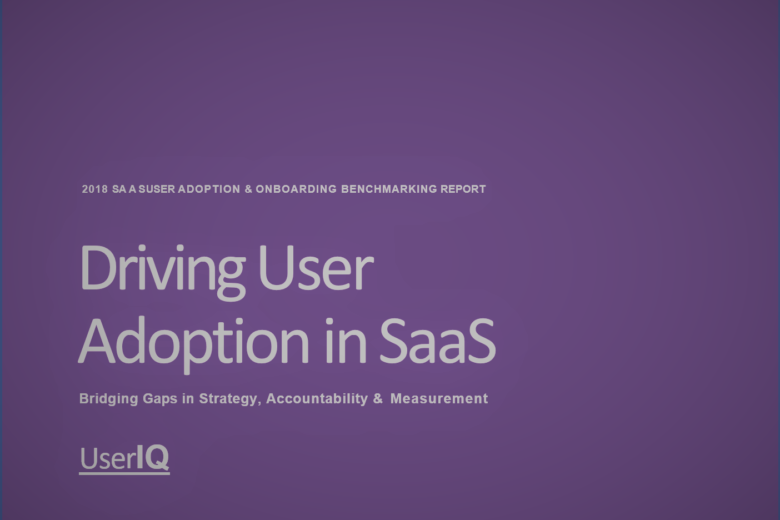
アダプションの大御所 レイチェルさんの会社 UerIQ社 が、アダプションの実態調査を行いました。調査レポートの中で注目すべき主要トレンドをレイチェルさん自身が紹介くださってます。
aash
日本でも大変注目を集めている、彼女の渾身なプレゼン記事「アダプションの努力の方向、間違ってませんか?: チャーン防止が目的なら要注意」と合わせてお楽しみください!
注:著者 Rachel Orston氏の許可を頂き原文の和訳を紹介します
ユーザーアダプション&オンボーディングトレンド2018
SaaS企業にとって定期収益(recurring revenue)は、失いたくなければ努力して維持すべきもの、そして、カスタマーと長期の関係を築きネガティブチャーンに持っていけるかは、企業が生き残り成長する力を測る新たな指標、ということは既に説明不要の周知の事実です。
一方、そういった周知の事実はアダプションに成功しなければ達成不可能である、ということは意外と知られていません。
アダプションは、カスタマーが事業目標を達成するために各ユーザーにプロダクトを使いこなせるようになってもらうためのプロセスです。プロセスを上手く進められれば、リテンション率が向上し、新たな収益機会がもたらされます。
アダプションは、長期的な収益成長の原動力です。アダプションに成功するまでの道のりでは、まずオンボーディングに成功することが必要不可欠であることも知られています。
にもかかわらず、各社がオンボーディングとアダプションをどの程度うまく推進しているかは意外と不透明です。アダプションに成功するための優先順位を正しくつけ、結果を評価し、常に改善する、という一連のプロセスを各社はどの程度上手く回しているのでしょう?
そういったことを調べるために私たちはアンケート調査を実施し、その結果をまとめて「ユーザーアダプション & カスタマーオンボーディング ベンチマークレポート2018」として公表しました。
調査から、「ユーザーアダプションは重要であるという認識」と「実際にどう行動しアダプションをどう測定・評価しているかの実態」の驚くべき乖離に関わる主要トレンド3つが検出されました。なお回答者の大半は、B2B市場(72%)のカスタマーサクセス担当者(65%)です。
この調査結果の中で最も衝撃的だったのは、回答者の実に74%は難度の高いユーザーアダプション問題に週の半分を費やしている一方、回答者のほぼ半数はユーザーアダプション戦略が無いと答えている点です。
つまり、カスタマーサクセス、プロダクトに加え、営業とマーケティングも含むSaaSプロフェッショナルな人たちが、彼らの膨大な時間を費やして総力でユーザーアダプションに取り組んでいるにも拘らず、彼らの行動の原動力となる戦略が不在なまま、試行錯誤の行動をしているということです。

以下に、調査で明らかになった具体的な主要トレンド3つをご紹介します。併せて、戦略と現実のギャップを埋めてユーザーアダプションに成功するためのお勧め方法についてもご紹介します。
トレンド1)みなオンボーディングをスケールさせたくて仕方ない
オンボーディングは、ユーザーの第一印象が決まり、タイム2バリューが短縮され、真のユーザーアダプションに不可欠なことが目白押しに実行される重要なフェーズです。ですが、カスタマー重視でなければならないこの重要フェーズで、プロダクト重視なオンボーディングが展開される、というアルアルな失敗例を本当によく見かけます。
オンボーディングは、ユーザーがベストな機能をできるだけ早く見い出し、最終的にその機能を使い倒すことで事業目標の達成に繋がる価値を手に入れられるよう、プロダクトオーナーがユーザーを支援する期間です。つまりオンボーディングはユーザーアダプションにおける重要な「変曲点」です。
このことが念頭にあるためと思いますが、回答者の70%は「オンボーディングの改善が今年の最優先事項」と回答し、26%は「セルフサービス/ハイテクオンボーディングモデルの開発を具体的に検討している」と答えました。
オンボーディングチームの72%は1?10人で構成されていることを踏まえると、この回答は理にかなっています。なぜなら、チーム規模が比較的小さいため、”白い手袋アプローチ(訳者注:カスタマーを下にも置かない様な至れりつくせりの丁寧な対応をする)” を長期に展開すると業務があっという間に溢れるからです。
オンボーディングのスケーラビリティを上げたいなら、ごく一部の領域をまず自動化し、そこでユーザーには何が最適かを学び、そしてその領域を広げていくことです。
現在、ハイタッチ戦略に頼っているチームの多くは、ヒューマンタッチが機能する領域をロボットや無味乾燥な自動応答に置き換えることに不安を覚え自動化をためらっています。その気持ちはわかります。なので私は、テックタッチをハイタッチに置き換えるのでなく、ハイタッチ戦略の一環としてそれを補完したり強化するのに用いることを提案します。
人は新しいことを習慣にするには何度も何度も同じことを耳にする必要がある、という事実を忘れないでください。新しいことの習慣化を手助けする手段としてテックタッチの活用を検討してみましょう。
トレンド2)みなアダプションの測定・評価に苦戦している
カスタマーが期待成果を手にするためにどれくらい上手くプロダクトを使いこなせているか、? 例えば、ユーザーが「うわ、すげえ!」と叫ぶ瞬間(ワオの瞬間)を早々に経験しどれだけサッサと投資回収できているかなど、を測定するのは、実は非常に重要な上でとても難しくもあります。
アダプションの測定方法を考えるには、統合的な視点のアプローチが必須です。オンボーディング戦略の目的は、カスタマーがプロダクトを沢山利用することではなく、カスタマーが事業上の価値を実現することです。つまりアダプションの測定値は、カスタマーが実現したいと考えている価値やその考え方自体を反映するものでなければなりません。
オンボーディングの成否、TTL(Time-to-Value;うわ、すげえ!と叫ぶまでの所要時間)、そしてユーザー感情、これらすべてをセットでトラッキングする必要があります。一方、大抵の企業はこういった指標をトラッキングしていない、もしくは、そもそも何を測定すればよいかも分かっていないため「アダプションを測定するのはとても難しい」と感じています。
私たちの調査で「オンボーディングの進捗状況を測定・把握している」と回答したのはたった33%です。18%はオンボーディングプロセスを全く評価しておらず、48%はカスタマーへ電話をして状況を聞くのみと回答しています。
であれば、「アダプションの測定はとても難しい」と感じるのも無理ありません。そしてそれは、カスタマーに価値ある成果を手にしてもらう上で多くの企業が重要な機会を逸していることを意味します。
また、回答者の大半は、ユーザーアダプションを改善したいが、「可視性」「データ」「VoC」「ユーザー分析」が欠如していることが最大の課題と回答しています。適切なデータを入手し、それを組織内の必要部署に適切に展開する方法がなければ、企業はベンチマークをしたり改善領域を理解することができません。
同調査の実に約4分の3の回答者が「今年はアダプションの改善が最優先事項だ」と答えています。そういう方にとり、 データ欠如の問題を解消し、適切な指標を定義して評価方法を確立すること、がまずはスタートポイントになりそうです。
評価方法を検討する際は必ず、プロダクト利用状況と事業価値の実現度との整合性を確認しましょう。カスタマーがあなたのプロダクトを契約する際に設定した期待値こそが、成功度を測るKPIになりそうです。
トレンド3)みな実はアダプションに重点も説明責任もおいてない
私たちが最も注目する問題点は「説明責任の欠如」です。
回答者のたった19%だけが「オンボーディング専任チームがある」と回答しています。
即ち、ほとんどの企業が、カスタマーがプロダクトを上手く使いこなすことを保証する真の責任を負っていないのです。専任チームがないのは、「ワークフローが混乱するから」、「ユーザーエンゲージメントプログラムをシンプルにしたいから」、「内部リソースが確保できないから」、「管理サポートできないから」、「予算を調達できないから」が理由と答えています。
という状況であれば、ユーザーアダプションのパターンに優先順位をつけて可視性を高めるのにみんな苦労しているという事実に全く驚きません。
であれば、Why(ユーザーがプロダクトを購入した理由)と What(ユーザーがプロダクトでしたいこと)を整合させ、「すげえ!」と叫ぶ瞬間までのROIを上げて、ぜったい契約更新したいと思わせるのにみな苦戦するはずです。
みなさんがユーザーアダプションやオンボーディングを改善したいと思っているのは明らかです。しかし、戦略と実態に大きなギャップがあることを見落としています。つまり、プロセスそのものが、スケーラブルでも、データドリブンでも、統合的アプローチでもないものになっているのです。
この状況を軌道修正するために私たちがお勧めするアクションは以下の通りです:
1)アダプションは「トップダウンかつ組織横断がマストな取り組みである」ことを肝に据える
経営メンバーがアダプション戦略に関与していない場合、アダプションは公式プロセスではなく、組織の最優先事項でもない可能性が大です。
アダプションを成功させるにはさまざまなKPIが必要で、それらを測定するには複数の機能組織の協力が不可欠なため、組織横断のアダプションチームによるリードのもと、組織全体が一丸となってアダプションに取り組まなければなりません。
まずはカスタマーサクセス、プロダクト、営業、マーケティング、オペレーションなどの主要部門から利害関係者を集め、組織横断な視点でユーザージャー二―をマッピングし、全社視点のギャップを組織の共有理解にしましょう。
2)トレーニング&導入の専任チームを立ち上げる
オンボーディングはアダプション成功までの道のりにおける重要マイルストーンですので、専任チームとそのリーダー、具体的な実行計画を用意し、集中して実行することが必須です。
私たち調査で「専任オンボーディングチームがある」と答えた回答者は19%です。逆に残り8割は、専任チームや実行計画そしてリーダーシップが不在です。カスタマーセグメント単位でオンボーディングへどれだけ投資するのか、そしてその時間軸を明確にし、オンボーディング担当者がしっかり仕事できるよう十分なリソースを確保しましょう。
3)テックタッチを可能なところから採用する
テックタッチは、ハイタッチに比べはるかにスケーラブルかつ積極的な施策を展開できます。いま現在ハイタッチでしていることをテックタッチに置き換えられないか、その可能性を吟味しましょう。
便利なテクノロジーを活用すれば、客観データに基づいてカスタマーの状況を理解し、ユーザーをきめ細かく評価し、ニーズに応じたパワフルなアダプション戦略を立てられます。
より積極的なエンゲージメントを自動化できるだけでなく、カスタマーサクセスマネジャーの貴重な時間をカスタマーの戦略パートナーとしてより価値ある行動に振り分けることができるのです。
4)適切なKPIに注目し継続的にトラッキングする
サインアップ状況と利用状況だけをKPIに設定したなら、プロダクトが果たして価値を出しているのか、アダプションが成功しているのか、といった重要な事実を把握できません。正しい海図が手に入らなければ、誤検出や誤セキュリティ感覚に陥ります。
Time-to-Value(TTV)、期待成果の達成度あい、カスタマーの感情、円滑なカスタマー体験などをしっかり追跡し、統合的に状況を測定しましょう。
以上4つのアクションをご紹介しました。
この4点に関し他社比較をしてみてください。他社がどう上手くアダプションを実施しているか(またはしていないか)の興味深い結果が判明します。そして、ベンチマークと比較しながら「はたして自分は長期的な視点でアダプションを推進できているだろうか?」と自問してみてください。あなたのアダプション実務が今どのレベルに位置するのか深く理解できることでしょう。