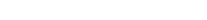先月公表された (旧)投資銀行 パシフィッククレスト社 (2016年よりKBCM Technology Group) による「2017 Private SaaS Company Survey Results」に関する第2回目の記事はコスト構造についてです。
第2回 コスト構造 ←今回はこれ
上場企業であれば決算資料から紐解けるコスト構造ですが、未上場企業のコスト構造は闇に包まれているため、大変貴重なデータです。ただしサービス単価や、競争の激しさ、事業展開フェーズなどによってコスト構造は大きく異なるのも事実なので、全体平均を見てもなかなか意味を捉えきれないデータでもあります。
そこで今回は SaaS企業調査2017のコスト構造データを紹介すると同時に、私の独断で選んだ上場SaaS企業3社をピックアップし同社のコスト構造も合わせて比較してみることにします。
未上場SaaS企業調査の対象企業のコスト構造(平均)

粗利 73%、営業費用 82%、営業費用の内訳はマーケティング&セールス 35%、R&D 28%、販管費 19%です。なお多様な企業の平均値ですが、2014年から数値に変化はほとんどありません。
初めてこの数字を見た時、私は衝撃を受けました。なぜって売上100円あげる毎に10円の損失を出しているわけです。私は職業柄、日本の大企業さんとお仕事してきたため、このような利益構造(というか損失構造)には驚きが先行してしまいました。
同企業の企業規模別コスト構造

未上場企業が対象のため、売上規模は大きくて$60MM(約70億円)です。
その上で面白いのは、粗利と営業費用合計の比率は規模別に見てもほとんど変わらないのに対し、営業費用の内訳構成が規模によって相当変わる点です。具体的には規模が大きくなるほどマーケティング&セールスの比率が上がり(33% → 43%)、逆にR&Dと販管費の比率(合計で51% → 36%)が下がります。
これは、企業が成長するにつれ業務の効率化が進み規模の経済を獲得できるからと思われます。
一方、売上成長は大きく減速(54% → 26%)します。成長するにつれ、マーケティング&セールスへ相対的に多く投資できるようになるものの成長の爆速スピードを維持するのは難しいということです。
背後には先の記事「SaaS企業にとって”Good”なリテンションとは (2)」で紹介した「偽善 (false positive)問題」が鍵を握っていそうです。(この記事は本当に意味深いのでSaaS事業の方はぜひ読んでください!)
簡潔に言えば、小さな企業 ≒ 創業間もない企業は新規カスタマーの比率が非常に高いため、グロスレベニューリテンションが構造的に大変良い水準を維持し続け、売上も急成長し続ける。しかしそこで油断し見せかけのリテンション水準の裏に潜む本当のリテンション力を早い段階で自覚せずカスタマーサクセスに着手せずにいれば、早晩リテンション率の悪化と共に売上成長スピードの限界に至るのです。
上場SaaS企業のコスト構造:ベンチマーク

同調査では、パシフィッククレスト社が独自に選定した上場SaaS企業(お手本企業)のコスト構造の定点観測データも紹介されています。
上場企業なので大区分は売上$100MM(約120億円)超です。お手本としてその大区分を見ると、粗利 67%、営業費用 78%、先の未上場企業と同様、営業損失1割。つまり売上が三桁億円に達してもまだスタートアップの利益構造です!
ただ流石に上場というハードルを乗り越えた企業だけあり、三桁億円規模へ成長してもなお売上成長率36%を維持しています。
今やVCの方々も投資先企業のチャーン構造から本物のリテンション能力をじっくり見極めるため、先に述べた「偽善問題」を克服しカスタマーサクセスを組織的に推進できている企業が結果としてエグジットを遂げ、上場後も高い成長率を維持できていると考えられます。
以上が同調査2017で紹介された未上場SaaS企業と上場SaaS企業のコスト構造分析です。復習をかね主要数字を以下に図示します。

事例1:Salesforce.com のコスト構造
ここからは同調査結果を離れ、私の独断で上場企業3社を取り上げ、そのコスト構造を観察してみたいと思います。最初は SaaSの雄 Salesforce.com社です。
調査結果と比較できるよう同じフォーマットを使います。

こうしてみると、やはりセールスフォースの凄さは一目瞭然です。
まず目につくのは粗利の高さ(75%〜)で、先の上場お手本企業のベンチマーク(67%)より更に高いです。それでいて営業費用はベンチマークより低く、更にここ数年は改善傾向です。
そして何より凄いのは、直近の数年、コスト構造が大きくブレることなく利益ある成長(損失1割ではない!上で直近でも2-3割成長)を続けている点です。
もちろん事業ドメインの良さによる面も大きいですが、それだけですべて説明はつかないと思います。やはり、R&Dと販管費に規模の経済を効かせて大きく抑えつつ、マーケティング&セールス(にカスタマーサクセスのコストも含むと想定)に正しくお金を使っている結果、高い粗利と売上成長率を達成していると思われます。
事例2:Shopify のコスト構造

2015年に上場し日本でも認知のある同社は、SaaSの中でもプラットフォーム型ビジネスを展開している点がユニークです。
この図をみて直ぐ気づくのは、同社は上場前後で大きくコスト構造を変えている点です。特に R&Dだけでなく、マーケティング&セールスも大きく絞り、粗利も我慢しながら、上場後もなお”毎年倍増”という爆速成長を取りにいっている点が目を引きます。
事業戦略の視点でみると、とてもリーズナブルな月額課金設定などで出店店舗数の急拡大に注力し、結果、プラットフォーマーならではの規模の経済を最大に効かせてマーケティング&セールスを抑制し、広告決済などのサービス売上(アップセル&クロスセル)拡充に注力し、売上の爆速成長を維持しようとしていると考えられます。
個人的には、そのような事業戦略もさることながら、そのような事業戦略に合わせ 1-2年で大きくコスト構造をキュッキュッと変えてくるのは米国スタートアップらしいなあと感動しました。
事例3:Netflix のコスト構造

最後はNetflixです。流石に同社については説明不要ですね。そして3社目なので、パッと見て気づくのは、本当にスカスカな図です!!
Amazon Prime (streaming)を大きく抑え、特に米国家庭に深く入り込んでいるNetflixですが、その裏のコスト構造はSaaS企業の中でも大変ユニークです。
同社は2012年に瀕死状態に陥りました。同年、DVDレンタルからストリーミングサービスへと事業の軸足の大転換を果たすリスクを取りつつ、その価格設定がユーザーから受け入れられずに大きく袋叩きにあったのです。2011年に36%だった粗利が翌2012年(上図の通り)は27%と一気に1割悪化しました。
そこから数年かけ、直近は粗利もBeforeの水準へ回復しつつあります。特に昨年敢行した価格の値上げなども、事前は批判の嵐でしたが、蓋を開ければPLにきちんと反映されています。
凄いなあと思うのは、瀕死から蘇った後に大きな売上成長を果たしている点です。これは海外市場へ積極的に投資しユーザー獲得に成功したのが理由ですが、通常その手のGo-to-Market戦略は初期投資が非常にかさむと同時に海外拠点が各地に分散する結果、費用面で規模の経済が効かせにくくなる、にもかかわらずしっかり利益を残している点です。
Netflixについては、カスタマーサクセスの実務に関してもとても興味深い企業ですので、改めてフォーカスを当てた記事を紹介したいと思っています。
以上、未上場SaaS企業の調査結果と合わせ馴染みの上場3社のコスト構造を紹介しました。冒頭、コスト構造は平均値を見ても意味を捉え難いと言いましたが、逆に1社1社スポットライトを当てるとこれほど面白いデータはないと思います。
皆さんも今回の分析を参考に、お手本企業のコスト構造をチェックしてみてはいかがでしょうか。第3回目「利益ある成長 “40%ルール”」もぜひご覧ください!